「ねじ込み配管を施工したけど、水漏れしてしまった…原因がわからない」
「適切な寸法や規格が知りたいけど、情報がまとまっていなくて困る」
「シール材の選び方や巻き方の正しい方法を知りたい!」
そう思う方もいるかもしれません。
実は、ねじ込み配管の施工では、適切な寸法・規格の理解と、シール材の正しい使用が重要です。これらを誤ると、水漏れや強度不足といったトラブルが発生し、結果的に手間やコストが増えてしまいます。
この記事では、ねじ込み配管の基本について解説し、寸法・規格の選び方、漏れを防ぐシール材の使い方、施工のコツを詳しく紹介します。正しい知識を身につけ、確実な施工を目指しましょう!
配管ねじ込みとは?基本を理解しよう
ねじ込み配管の特徴とは?
ねじ込み配管とは、金属管同士をねじによって接続する工法であり、特に小口径の配管に使用されることが多い。ガスや水道設備、空調配管など、幅広い用途に対応しており、歴史的にも長く採用されてきた技術である。
この工法の最大の特徴は、接続部において溶接やフランジ接合が不要である点である。現場での作業性が高く、特別な設備を必要とせずに施工できるため、小規模な配管工事にも適している。しかし、接続部にねじがあるため、他の工法と比べると強度や耐圧性が若干劣る場合がある。
ねじ込み配管の利点としては、施工が比較的簡単であり、配管の取り外しや交換が容易であることが挙げられる。一方で、接続部の密閉性がシール材に依存するため、適切な施工を行わなければ漏れのリスクが高まる。特に、施工時の締め付けトルクやシール材の選定を誤ると、後々のトラブルにつながるため注意が必要である。
ねじ込み接続が使われる場面
ねじ込み配管は、主に以下のような場面で使用される。
まず、一般住宅の給水・給湯配管である。特に古い建物では、銅管やポリエチレン管が普及する以前の配管としてねじ込み配管が用いられていた。現在でも、一部の改修工事や設備の増設時に採用されることがある。
次に、工場や施設の設備配管においても活躍している。圧縮空気やオイルの配管として使われることが多く、定期的なメンテナンスが求められる設備においては、取り外しや交換のしやすさがメリットとなる。
また、DIYやリフォームの分野でも利用されることがある。例えば、家庭内での水道修理や自作の配管設備を構築する際、ねじ込み接続は手軽に導入できる工法のひとつとして選ばれている。
ねじ込み配管の寸法と規格|選び方のポイント
ねじ込み配管の主な寸法規格とは?
ねじ込み配管の寸法や規格を正しく理解することは、施工ミスを防ぎ、適切な接続を行うために不可欠である。日本国内で一般的に使用されるねじ込み配管の規格として、日本工業規格(JIS)が定める JIS B 0203(管用テーパねじ) や JIS B 2301(鋼製ねじ込み継手) などがある。
JIS規格におけるねじ込み配管の基準
JIS B 0203 では、ねじの種類として 管用テーパねじ(PTねじ) が規定されており、この規格に基づいたねじ込み継手が一般的に使用される。管用テーパねじは、ねじ山の角度が一定の勾配を持ち、締め込むことで密着度が増す仕組みとなっているため、流体の漏れを防ぐ効果がある。
一方、JIS B 0202 には 管用平行ねじ(PFねじ) が含まれるが、これは主に機械部品の接続などに用いられ、配管の接続には適さないことが多い。施工時には、テーパねじと平行ねじを混同しないよう十分に注意が必要である。
寸法を間違えるとどうなる?失敗例と注意点
ねじ込み配管において、寸法を誤ると接続不良が発生し、重大なトラブルを招く可能性がある。例えば、適合しない規格の継手を使用すると、以下のような問題が生じる。
- ねじのかみ合わせが悪くなり、締め込んでも 漏れが発生する
- 過度な力で締め付けることで ねじ山が破損する
- 不適切な寸法の継手を使用すると、 配管全体の耐圧性が低下する
このようなミスを防ぐためには、事前に使用するねじの規格や寸法を確認し、適切な部品を選定することが重要である。
適切な寸法・規格を選ぶ方法
ねじ込み配管の寸法・規格を選ぶ際には、まず 使用する流体の種類 を考慮する必要がある。例えば、水道やガスなどの圧力を伴う流体を扱う場合、JIS B 0203 の管用テーパねじが適している。
次に、接続する配管と継手が同じ規格であることを確認する ことが必須である。異なる規格のねじを接続すると、漏れや破損のリスクが高まるため、施工前に仕様書やカタログをよく確認し、統一された規格のものを選ぶことが望ましい。
さらに、圧力条件に適した材質・寸法を選ぶ ことも重要である。高圧環境下では、肉厚のある強度の高い配管や継手を使用し、シール材の選定にも注意を払う必要がある。
ねじ込み配管のシール材の種類と正しい使い方
シール材の役割と重要性
ねじ込み配管の接続部において、シール材は 漏れを防ぐための重要な役割 を果たす。ねじ込み部は完全な密閉構造ではなく、ねじ山のすき間から流体が漏れ出す可能性があるため、適切なシール材を使用することで密閉性を確保する必要がある。
シール材の選定を誤ると、施工後に漏れが発生し、配管のやり直しが必要になることがある。また、適切な量を使用しないと、逆にねじ込み部の過剰な締め付けにつながり、ねじの破損や配管のゆがみを引き起こすリスクもある。そのため、施工環境や使用する配管の種類に応じて、適切なシール材を選択することが重要である。
ねじ込み配管に使われるシール材の種類
ねじ込み配管の施工で一般的に使用されるシール材には、大きく分けて シールテープ(フッ素樹脂テープ) と 液体シール材 の2種類がある。それぞれの特性や使用方法について理解し、適切な場面で使い分けることが求められる。
シールテープの特徴と使い方
シールテープは、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)素材でできた薄いテープ状のシール材であり、ねじ山に巻き付けて使用する。主な特徴として、次のような点が挙げられる。
- 施工が簡単で、初心者でも扱いやすい
- 耐薬品性が高く、幅広い用途に対応できる
- 巻き方を誤るとシール性能が低下するため、均等に巻くことが重要
適切な巻き方としては、ねじ山に沿って 2~3回均等に巻き付ける のが理想的である。巻きすぎるとねじが適切に締め込めなくなるため、適度な厚みに調整することがポイントとなる。
液体シール材の特徴と使い方
液体シール材(シール剤)は、ねじ山に塗布することで硬化し、すき間を完全に埋めるタイプのシール材である。主な特徴は以下の通り。
- 流動性があるため、ねじ山のすき間に均等に密着する
- 乾燥・硬化後に強力な密閉性を発揮する
- 固着性が強いため、後で取り外しが難しくなる場合がある
施工時には、ねじ山の汚れや油分をしっかりと拭き取り、清潔な状態にした上で 薄く均等に塗布する ことが重要である。また、完全に硬化するまで時間がかかるため、施工後すぐに圧力をかけるのは避けるべきである。
漏れを防ぐシール材の正しい施工手順
シール材を適切に使用することで、ねじ込み配管の漏れを防ぐことができる。以下の手順を守ることで、確実な施工が可能となる。
- ねじ山の清掃
配管や継手のねじ山に付着したゴミや油分を完全に除去する。汚れが残っていると、シール材の密着性が低下し、漏れの原因となる。 - シール材の選定
配管の用途や施工条件に応じて、シールテープまたは液体シール材を選択する。特に高温・高圧環境では、耐熱性や耐圧性のあるシール材を使用することが望ましい。 - シール材の適切な適用
- シールテープの場合:ねじ山に沿って 均等に2~3回巻く。巻きすぎると締め付けに影響が出るため注意が必要。
- 液体シール材の場合:ねじ山に 薄く均等に塗布 し、施工後 完全に硬化するまで待つ。
- 適切な締め付け
シール材を使用した後、適切な締め付けトルクでねじ込みを行う。過度な締め付けは、ねじ山の破損や配管のゆがみを引き起こす可能性があるため、慎重に行う。 - 漏れの確認
施工後、圧力をかけて漏れがないかテストする。特に水圧や気密試験を行い、問題がないことを確認してから運用を開始する。
ねじ込み配管の施工手順|漏れを防ぐコツと注意点
施工に必要な工具と準備
ねじ込み配管を適切に施工するためには、適切な工具と事前の準備が不可欠である。施工時に必要な工具と、それぞれの役割を理解しておくことが重要である。
必要な工具一覧
- モンキーレンチ・パイプレンチ:配管の締め付けに使用し、適切なトルクで固定するための工具。
- ねじ切り機(ダイス):新しい配管にねじを作るための工具。既存のねじ込み継手と接続する場合、正しい規格のねじを作ることが必要。
- シール材(シールテープ・液体シール剤):ねじ山の密閉性を高め、漏れを防ぐために使用。
- 掃除用具(ワイヤーブラシ・ウエス):ねじ込み部の汚れや油分を取り除くために必要。
施工前の準備
- 使用する配管と継手の規格・寸法を確認し、適合するかどうかを事前にチェックする。
- ねじ山の清掃を行い、異物が付着していない状態にする。
- シール材を適切に準備し、施工時にスムーズに使用できるようにしておく。
適切な工具と準備を整えることで、施工時のトラブルを未然に防ぐことができる。
ねじ込み配管の正しい施工手順
ねじ込み配管の施工には、いくつかの重要なステップがある。これらを順番に正しく行うことで、漏れのない確実な接続が可能となる。
ねじ込み作業の基本ステップ
- ねじ山の確認と清掃
施工前に配管と継手のねじ山をチェックし、異物や錆がないことを確認する。必要に応じて、ワイヤーブラシやウエスを使用して清掃する。 - シール材の適用
適切なシール材を選択し、ねじ山に均等に塗布する。シールテープの場合は 2~3回巻き、液体シール材の場合は 薄く均等に塗布 して完全に乾燥させる。 - ねじ込みの実施
配管と継手をねじ込み、手で締め付けられるところまで回す。その後、パイプレンチを使用して適切なトルクで締め付ける。過度な力を加えすぎると、ねじ山が損傷する恐れがあるため注意が必要。 - 締め付けトルクの管理
適切な締め付けトルクを維持することで、漏れや破損を防ぐことができる。メーカー推奨のトルク値を参考に、過不足のない締め付けを心掛ける。 - 漏れの確認
施工完了後、配管に圧力をかけて漏れがないかをテストする。水圧試験やエアテストを実施し、異常がないことを確認してから使用を開始する。
適切な締め付けトルクの管理方法
ねじ込み配管の締め付けは、適切なトルクで行うことが重要である。締め付けが弱すぎると 接続部から漏れが発生 し、強すぎると ねじ山が破損し、配管自体の強度が低下 するリスクがある。
適切な締め付けを行うポイント
- 手締めの段階でしっかりと回せるか確認し、無理に締め込むことを避ける。
- 締め付ける際は、過度な力を加えずにパイプレンチで適度に回す。
- メーカーの推奨トルク値を参考にし、必要であればトルクレンチを使用する。
施工時に適切なトルク管理を行うことで、漏れや破損のリスクを大幅に低減できる。
施工時のよくあるミスとその回避策
ねじ込み配管の施工では、いくつかのよくあるミスがある。これらの失敗を回避するためには、事前の確認と慎重な施工が求められる。
シール材の巻きすぎ・巻かなすぎ
シールテープの巻きすぎは、ねじ山のかみ合わせを悪くし、適切に締め込めなくなる原因となる。一方で、巻きが少なすぎると密閉性が確保できず、漏れの原因となる。適切な回数で均等に巻くことが重要である。
締め付け不足・過度な締め付け
締め付け不足では接続が不十分になり、振動や圧力によってゆるみが生じることがある。逆に、過度な締め付けはねじ山を破損させる可能性があり、修復が困難になることもある。適切な力加減を意識して施工することが大切である。
ねじ込み部の汚れや異物の放置
施工前にねじ込み部を清掃せずに作業を進めると、異物が噛み込んで密着度が低下し、漏れやねじの破損を引き起こす可能性がある。施工前には必ず清掃を行い、ねじ山を確認しておくことが重要である。
ねじ込み配管のよくあるトラブルと対処法
ねじ込み配管は施工が比較的容易である一方で、適切な方法で行わないとさまざまなトラブルが発生する可能性がある。ここでは、よくあるトラブルの原因とその対処法について解説する。
配管の漏れが発生する原因と対策
ねじ込み配管で最も頻繁に発生する問題が 漏れ である。施工直後に漏れが発生する場合もあれば、数ヶ月、数年後に発生することもある。主な原因と対策を見ていこう。
シール材の施工ミスによる漏れ
ねじ込み配管の密閉性は、シール材の適用方法に大きく左右される。以下のような施工ミスが原因で漏れが発生することがある。
- シールテープの巻き方が不適切:巻きすぎるとねじ山がかみ合わず、締め付けが不十分になる。逆に巻きが足りないと、十分な密閉ができず漏れの原因となる。
- 液体シール材の塗布量が適切でない:塗布量が少なすぎると密閉効果が弱まり、多すぎると固着しすぎてねじ込みが適切に行えなくなる。
- シール材の選定ミス:高温・高圧環境に適したシール材を使用しないと、経年劣化が早まり漏れの原因になる。
対策
- シールテープは 2~3回均等に巻く のが理想的。巻き始めの位置を適切に調整し、ねじ山の根元までしっかりカバーする。
- 液体シール材は 薄く均等に塗布 し、乾燥時間を守る。完全に硬化する前に圧力をかけると漏れの原因になる。
- 環境に適したシール材を選定する。特に 高温・高圧環境では耐熱性のあるシール材 を使用する。
ねじ込み部の摩耗や劣化が原因の漏れ
経年劣化によってねじ山が摩耗すると、シール材を適切に施工しても漏れが発生しやすくなる。特に 古い配管の再利用 を行う場合、ねじ山が損傷していることが多いため注意が必要である。
対策
- 古い配管を再利用する際は、ねじ山の状態を確認 し、摩耗や損傷が激しい場合は交換を検討する。
- 施工前にねじ部の 清掃と防錆処理 を行い、異物の付着を防ぐ。
- 漏れが発生しやすい接続部には 二重のシール処理(テープ+液体シール材) を行う。
配管のねじ込みが固着して外れない場合の対処法
ねじ込み配管は、長期間使用していると固着して外れなくなることがある。これは、配管内の錆や腐食、シール材の硬化によってねじ部が一体化してしまうためである。無理に外そうとすると、配管が破損するリスクがあるため、適切な方法で取り外すことが重要である。
対策
- 潤滑剤(浸透オイル)を使用する:固着したねじ山に 潤滑剤を浸透させ、時間を置いてから緩める。特に錆が発生している場合、有効な手段となる。
- 温度変化を利用する:金属の膨張・収縮を利用して固着を緩める。バーナーなどでねじ部を軽く加熱 し、膨張・収縮を繰り返すことで緩めやすくなる。ただし、可燃性の配管では使用しない。
- 適切な工具を使用する:無理に力をかけるとねじ山が破損するため、パイプレンチやウォーターポンププライヤー を使い、徐々に回す。
ねじ込み部のゆるみを防ぐメンテナンス方法
施工後、時間の経過とともにねじ込み部がゆるむことがある。これは、振動や温度変化による膨張・収縮 が原因となることが多い。ゆるみが生じると漏れのリスクが高まるため、適切なメンテナンスを行うことが重要である。
対策
- 定期的に増し締めを行う:特に振動の多い環境(工場配管など)では、定期的にねじ部の締め付け状態を確認し、必要に応じて増し締めを行う。
- ねじ込み部の点検を実施する:目視での確認だけでなく、接続部の漏れテスト(石鹸水テストなど) を定期的に行い、早期に異常を発見する。
- 適切なシール材を使用する:ゆるみやすい環境では、液体シール材を併用 し、接続部の安定性を高める。
ねじ込み配管を成功させるためのチェックリスト
ねじ込み配管の施工を成功させるためには、事前準備から施工後の確認まで、細かな点に注意を払う必要があります。以下のチェックリストを参考にすることで、漏れやトラブルを防ぎ、確実な配管施工を実現できます。
施工前に確認すべきポイント
- 配管の寸法と規格が適切か確認する
施工を始める前に、使用する配管、継手、シール材がすべて適切な寸法・規格であるか確認することが最も重要です。規格が合わないと、施工後に漏れや強度不足の原因となり、再施工が必要になります。 - シール材の選定が適切か
使用する流体(給水、ガス、オイルなど)に合ったシール材を選ぶことが必須です。シール材は耐圧性や耐熱性が求められる場合もあるため、必要に応じて 高圧用シール材 や 耐熱性のシールテープ を選定しましょう。 - 工具や準備物が整っているか確認する
施工に必要なモンキーレンチやパイプレンチ、シール材、掃除用具がすべて準備されているかを再確認します。道具が不十分だと、施工中に時間がかかり、ミスを生む原因にもなります。 - ねじ山の清掃を行う
施工する配管と継手のねじ山に汚れや油分が残っていないか確認し、清掃します。ねじ山に異物が残っていると、ねじのかみ合わせが悪くなり、接続が不完全になる可能性があります。
施工後のチェック方法とメンテナンスのコツ
- 漏れテストを実施する
施工後、圧力をかけて漏れがないか確認することは非常に重要です。特に水圧や気密テストを行うことで、漏れが発生していないかを確認できます。テストは十分な時間をかけて実施しましょう。 - 適切な締め付けトルクを確認する
施工後、ねじ込み部が適切に締め付けられているかをチェックします。適切なトルクで締めることができていない場合、漏れや破損の原因になります。トルクレンチを使用し、メーカー推奨のトルク値でしっかり締めましょう。 - 定期的なメンテナンスを実施する
配管の施工後は、定期的なメンテナンスが必要です。特に振動や温度変化のある環境では、ねじ部のゆるみや劣化が進行する可能性があるため、定期的に点検し、必要に応じて 増し締め や シール材の再施工 を行いましょう。 - 接続部の劣化に注意する
長期間使用する中で、ねじ山の摩耗やシール材の劣化が進むことがあります。定期的に接続部の状態を確認し、必要であれば部品を交換することが重要です。特に 高圧配管 や 高温環境下の配管 では、劣化が早く進むことがありますので、早期発見と対策が求められます。


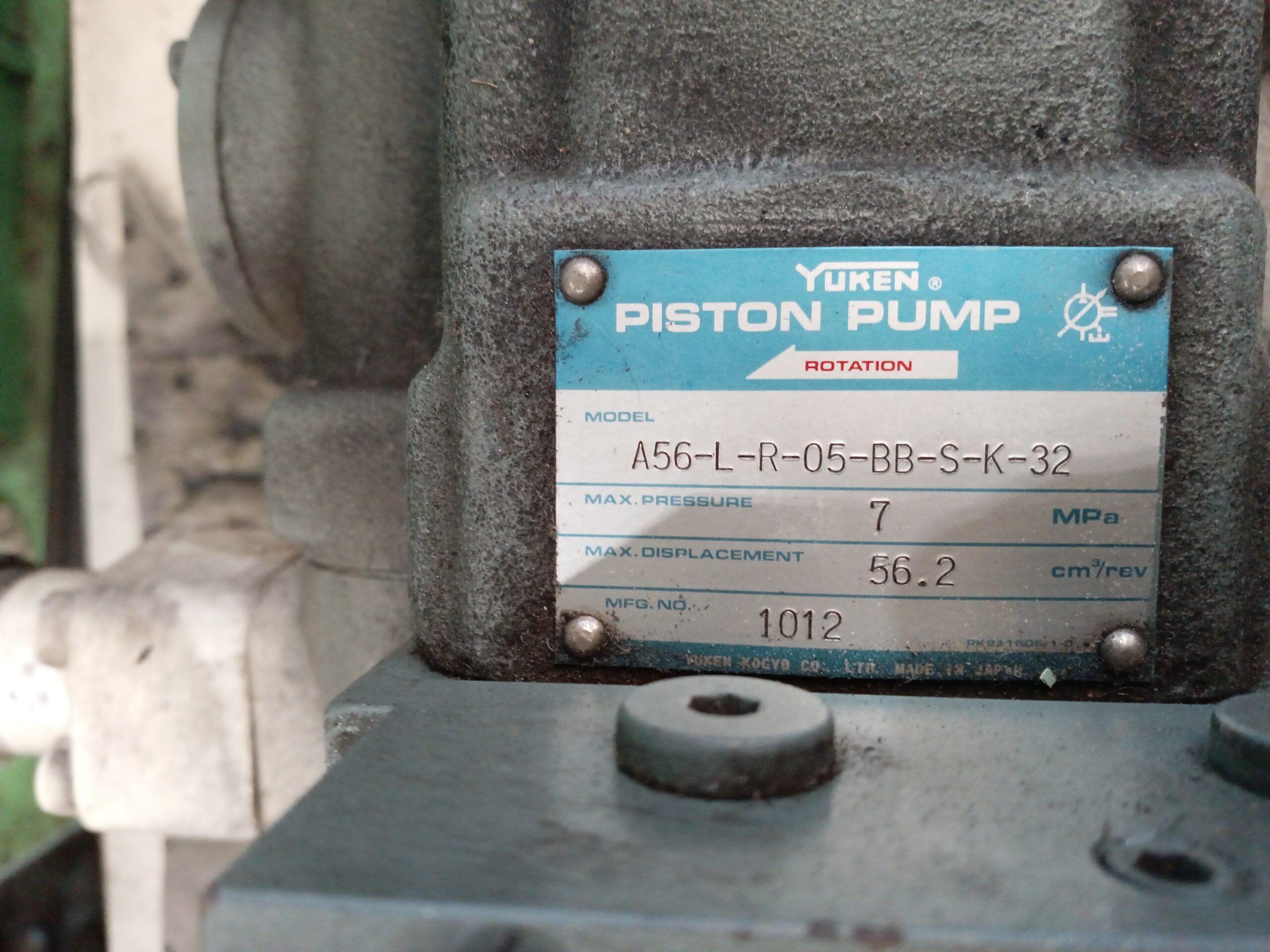
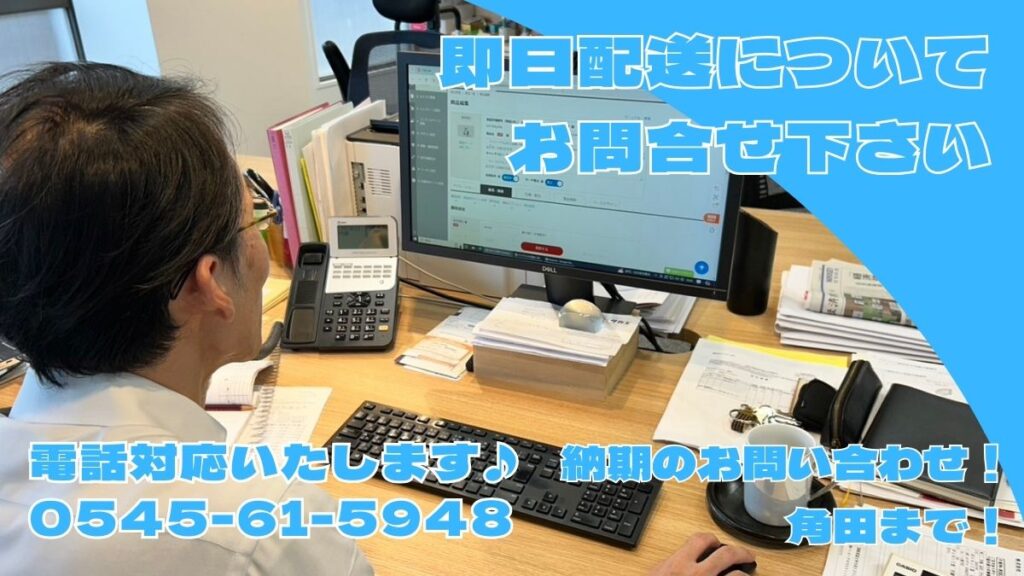







この記事へのコメントはありません。